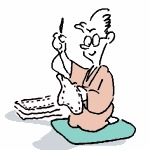 母(姑のこと)の形見分けは、生前にご縁のあった方々に、思い出のものをお持ちいただいて、事無く済ませることができた。
母(姑のこと)の形見分けは、生前にご縁のあった方々に、思い出のものをお持ちいただいて、事無く済ませることができた。
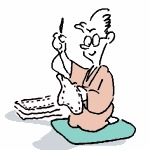 母(姑のこと)の形見分けは、生前にご縁のあった方々に、思い出のものをお持ちいただいて、事無く済ませることができた。
母(姑のこと)の形見分けは、生前にご縁のあった方々に、思い出のものをお持ちいただいて、事無く済ませることができた。
あとに残った品々は、私がいただいた。見れば、どれも長く使っていたものだけに、母の平常の暮しや、人生を垣間見る思いであった。浴衣や、しみの残る帯は、孫と遊ぶ時の笑顔を、洗いざらしのエプロンは、庭で花を愛でる姿を思い出す。ねまきは、母、家族共につらかった最後の10ヶ月の入院生活と重なり、胸が痛む。どの品も、母を偲ぶに十分なものばかりである。
しかし、今の私の生活に直接必要なものはない。かと言って、押入れにしまっては、器用な手先で、ものを再生し、大事に使った母の暮らし振りに対して申訳ない気がする。
ねまきや浴衣は、おむつや雑巾にして、必要な方に使ってもらいたい。平常着や帯、和装用小物は、養護学校の生徒さんの劇の舞台衣装に、白地のものは、草木染の材料に使っていただこう。熱演する舞台と、可愛い小物に変身した染物が、文化祭を盛り上げてくれたら嬉しい。手拭い・ハンカチ・風呂敷は、タンザニヤ訪問の時に持参し、村民との交流で役立ち、喜ばれた。一枚の布きれで心の通い合いが生まれるのである。
おむつを縫っていると、つぎ当ての針目に明治生まれの母の誇りが感じられる。私は、この一針毎に、昭和ひと桁生まれの人生を縫いこんでいるのだろうか。自分の老いや、このおむつを使う人のことが、しきりに思われる。形見の品が、本来の思い出や記念としてでなく、故人と無関係の方々に渡っていく。これも、明るく社交的で、人の話しの聞き上手な母に、ふさわしいことと思ったりする。
形見の品を通して、多くの未知の方々との出合いは、学ぶことがたくさんあった。私に、平常着の形見を残してくれた母に、心から感謝していることを、一周忌の墓前に、報告しようと思っている。