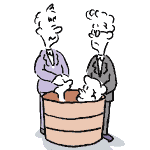 ボキッ。ボキボキッ。私はその音を庭で聞いた。冬空が真っ青だった。空気の姿がくっきりと見えるような青空に、母の両足の関節を折る音が響いた。残酷な音だった。母を土葬にする朝。座棺のため、近所の人々が母の両足を折って座らせる作業をしている音だった。啜り泣きの切れ間に、その音が聞こえてくる。ボキッ。ボキボキッ。その音が耳を襲うたびに、私の胸は複雑に揺れてた。何よりもその音が怖かった。それまでは、死というものじたいが他人事だった。それが、肉親でももっとも近い存在である母を突然失い、私はまだ、その意味をはかりかねていた。しかし、骨を折る音は衝撃で、私に「死」というものをはじめて実感させた。
ボキッ。ボキボキッ。私はその音を庭で聞いた。冬空が真っ青だった。空気の姿がくっきりと見えるような青空に、母の両足の関節を折る音が響いた。残酷な音だった。母を土葬にする朝。座棺のため、近所の人々が母の両足を折って座らせる作業をしている音だった。啜り泣きの切れ間に、その音が聞こえてくる。ボキッ。ボキボキッ。その音が耳を襲うたびに、私の胸は複雑に揺れてた。何よりもその音が怖かった。それまでは、死というものじたいが他人事だった。それが、肉親でももっとも近い存在である母を突然失い、私はまだ、その意味をはかりかねていた。しかし、骨を折る音は衝撃で、私に「死」というものをはじめて実感させた。母は2日前まで元気だった。餅をつき、あとは父を待つだけと、家中を整えた翌朝、母は突然倒れ、そして、あっさりと死んだ。一言もなかった。医師は脳溢血だと言った。訃報を聞き、大急ぎで帰郷した父は、変わり果てた母の前で、束の間、呆然としていた。母の骨を折る音を聞いたのは、その翌日だった。母が私たちに最後に残していく音が、両足を折る音。ボキッ。ボキボキッ。本当に残酷な音だった。それが、母の「死」だった。母は両足の骨を折られながら、もう、痛いとも言わない。そんな哀しいことがあるだろうか。しかし、それこそが「死」なのだろう。
晴天の冬空の下で、私は自分の耳に飛び込んでくる不気味な音を聞きながら、自分は生きているのだと思う。死んだ母が感じない痛みを、私が痛烈に感じている。ボキッ。ボキボキッ。その音が耳から入り、私の全身を駆けめぐり、もう呻き声一つたてようとはしない母の痛さを味わっている。読経が流れ、線香の匂いが鼻をつき、新たな涙で視界がぼやける時間になっても、私にはまだ、あの、骨を折る音が聞こえていた。ボキッ。ボキボキッ。
いまでも、時々あの音を思い出す。もう、30年という、長い時間が経過したというのに。