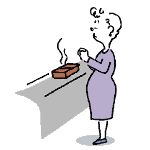 学生時代の親友の死はあまりにも突然のことであった。まだ26才だった。当時私は妊娠3ケ月で、つわりに悩まされ電車に乗ることさえつらい状態であった。「妊婦は葬儀に出てはいけない」そんなことを聞いた気がする。けれども、友人の死をこの目で碓かめるまでは信じたくないという感情は抑えようもなく、誰かに「出てもいいんだよ」と言ってもらいたくて、私は手当り次第に電話をかけた。「悲しみやショックがお腹にさわるよ」「私は身内の葬式にも出なかった」「死んだ人がお腹の子を連れていくって」。私の気持とは裏腹の返事ばかりを聞くうちに、私は、かえって行かなければ、という気持になった。あの時の心の動きは説明しようがない。ただ友人に会いたかった。お腹の子と一緒に彼女にさようならと言いたかった。死人が子どもを連れて行くなんてひどい迷信だ。私はそれを否定したかったのだ。
学生時代の親友の死はあまりにも突然のことであった。まだ26才だった。当時私は妊娠3ケ月で、つわりに悩まされ電車に乗ることさえつらい状態であった。「妊婦は葬儀に出てはいけない」そんなことを聞いた気がする。けれども、友人の死をこの目で碓かめるまでは信じたくないという感情は抑えようもなく、誰かに「出てもいいんだよ」と言ってもらいたくて、私は手当り次第に電話をかけた。「悲しみやショックがお腹にさわるよ」「私は身内の葬式にも出なかった」「死んだ人がお腹の子を連れていくって」。私の気持とは裏腹の返事ばかりを聞くうちに、私は、かえって行かなければ、という気持になった。あの時の心の動きは説明しようがない。ただ友人に会いたかった。お腹の子と一緒に彼女にさようならと言いたかった。死人が子どもを連れて行くなんてひどい迷信だ。私はそれを否定したかったのだ。通夜は、4月というのにひどく寒い、冷たい、雨の降りしきる中で行なわれていた。母の「迷信だけど…」との言いつけでお腹に小さな鏡を入れ、腹をそっと抑えながら私は式場に入った。学生時代の仲間たちは、皆寄り添って泣くばかりであった。私もやり場のない悲しみとこれは現実なのだという思いと、非情な寒さで体の震えが止まらなかった。あれほど悲しい経験を今までしたことは無かった。葬儀という悲しみの場に、妊婦が行くことはやはり体にも心にも良い事ではなかろう。ショックの大きさから考えても迷信とばかりは言えない気がする。だが親しかった人を見送りたい心はどうしようもないもので、無理がかからない様に気を付けて、短時間であれば良いのでないか。あれから時々、友人の夢を見る。元気に生まれた娘の年齢は、そのまま彼女がいなくなってしまってからの年数なのである。