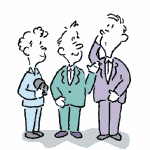 8年も独居し音信不通だった父が、東京近郊のC市で亡くなった。脳溢血だ。父の勤務先から電話を受け「とにかくすぐに伺います」。
知らない場所での葬儀とはいったものの、気は動転し、何から手をつけていいかわからない。そうだ、とりあえずお金だ。現金が必要だろう。
8年も独居し音信不通だった父が、東京近郊のC市で亡くなった。脳溢血だ。父の勤務先から電話を受け「とにかくすぐに伺います」。
知らない場所での葬儀とはいったものの、気は動転し、何から手をつけていいかわからない。そうだ、とりあえずお金だ。現金が必要だろう。これからまったく知らない町へ行って、遺体と対面し、葬儀を出さなければならない、いや葬儀は故郷でやるのか、どうやって遺体を運ぶのか、不安はつきない。
実家で一人暮らしの母と父の親戚へ電話を入れ、銀行で金をつくり、自宅へ戻る。黒服がどこにあるかわからない。妻は外出。仕方がない、平服で出かける。着いた先は、古物を扱う会社で敷地も広く、父はそこに住みこんで働いていた。社長はできた人で、葬儀はここで済ませろ、会社の施設を使って構わない、というありがたい申し出。
「それで父は?」あわてて、遺体とまだ対面していない。別棟に安置してあった遺体と対面。厳粛な一時。紹介された葬儀会社の人は親切で、何も知らない私に丁寧・適確に指導をいただいた。さあ、それからは忙しい。
明日は友引で、通夜を二回やらねばならない、埋葬許可証は取りに行ったか、読経の坊さんを依頼しなければならないが故郷の寺の宗派は何か、今夜は何人くらいの人が集まるのか、料理はどうするのか、お酒は、引出物は…。この忙しさは、どうだ。どたばたと相談し次から次へ決定。やはりプロでないと駄目だ。そのうち母もかけつけ、やっと安堵する。
まったく知らない場所で、知らない人と葬儀、しかも喪主としてである。ここでは勤務先の社長さんはじめ従業員の方の温かい協力がなければお茶一杯入れられず、場合によってはすぐに遺体を移動しなければならなかったかも知れない。
それと手際を心得た葬儀社の方の存在、これが何といっても大きかった。
お通夜は従業員の方の手作りの料理とお寿司。わんわんとみんな泣いて悲しんでくれた。不遇だった父も終りは良かったようだな、と思った途端、思わず涙が頬をつたわった。