家紋騒動記
[男性 61歳]
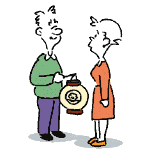 しっかり者の妻を失った義父は、久しぶりに集まった息子たちの姿に浮かれ、立ったり座ったり歩き回ったりで、全くの躁状態である。葬儀社の人は驚くほどてきぱきと、通夜葬儀万端の手順を整えていく。その中での流れを停めたのがこの家の宗旨である。
しっかり者の妻を失った義父は、久しぶりに集まった息子たちの姿に浮かれ、立ったり座ったり歩き回ったりで、全くの躁状態である。葬儀社の人は驚くほどてきぱきと、通夜葬儀万端の手順を整えていく。その中での流れを停めたのがこの家の宗旨である。
宗派が判かればそれによってお寺さんの手配をしてくれるのだと云う。然し仏壇も無いこの家で、手を合わせる機会も無く育って来た息子たちに、宗派の事など判ろう筈も無く、義父でさえ判然とした答えを出せないでいる。仏頂面の長男が、電話で母の死を伝えながら叔父にたずねる。
次の大きな引っかかりは、会葬御礼の印刷物に入れる家紋である。両親の紋服姿など見た事もない息子たちには、自分の家に紋のある事すら判っていない。再び長男の電話である。言葉で聞いただけの形も判らぬ家紋を、家紋帳をひろげた葬儀社の人が指で示して確認を求める。
「そうだわ、田舎のお祖母さんの肖像画は、たしかにこんな紋付きを着ていたわ。」
妻がきっぱりと云うと、かたわらから義父が、「うちにゃあ紋なんかないぞ。」と大声を出す。
兄弟たちの事はともあれ、年老いた両親の交際に関し、ある程度は知っていなくてはならないと痛感したのだった。小学生の頃、工作の時間に真鍮板を釘で叩き出し、家紋入りの表札を作ったことがある。我が家の「丸に橘」が難しく、簡単な家紋の友を羨ましく思ったものである。その工作のお陰で、わが家紋は強く脳裏にあるが、私の娘達は我が家の家紋など知らないのではなかろうか。
私は一計を案じた。言葉で教えるよりも形を示し、馴らしてしまうのが何よりと思う。そこで初詣の土産に家紋入りのミニ提灯を買い求め、部屋の隅に掲げておこう。娘たちは、それに拠って我が家の紋を認識する事だろう。彼女たちには嫁に行くまでの、わずかな期間の家紋ではあるが、私たち夫婦には生涯の「丸に橘」であるのだから。
Copyright (C) SEKISE, Inc.
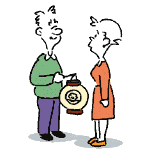 しっかり者の妻を失った義父は、久しぶりに集まった息子たちの姿に浮かれ、立ったり座ったり歩き回ったりで、全くの躁状態である。葬儀社の人は驚くほどてきぱきと、通夜葬儀万端の手順を整えていく。その中での流れを停めたのがこの家の宗旨である。
しっかり者の妻を失った義父は、久しぶりに集まった息子たちの姿に浮かれ、立ったり座ったり歩き回ったりで、全くの躁状態である。葬儀社の人は驚くほどてきぱきと、通夜葬儀万端の手順を整えていく。その中での流れを停めたのがこの家の宗旨である。