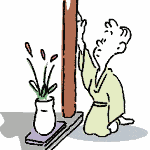 母は、発病以来12年間、3度の手術と、放射線療法、化学療法などの為入退院を操り返す日々を過してきた。この長く苦しい闘病生活に、やっと別れを告げたのは、“死”への出発であった。
母は、発病以来12年間、3度の手術と、放射線療法、化学療法などの為入退院を操り返す日々を過してきた。この長く苦しい闘病生活に、やっと別れを告げたのは、“死”への出発であった。8月。「お盆までもつかどうか危ぶまれる。」という医師の言葉を裏打ちするかの様に、母は、流動物すら飲み込むことが困難になった。衰弱は目に見えて現われ、医師は、IVH(中心静脈栄養)をするかどうか、同意を求めてきた。しかしこの時、私の脳裏をかけ巡っていたのは『母を家に帰したい。母を家で看取りたい』という思いだった。IVHを始めれば、病院を出ることは出来ない。私は、決断を迫られていた。母を家に連れ帰るということは、IVHはもとより、点滴もはずされ、母の命をつなぎとめていた医療行為の全てを取り去ってしまうことになる。さらに、母自身に与える精神的不安も気にかかった。しかし、迷っている時間はなかった。医師、ナースと相談の結果、私の、そして母の夢を、すぐ実行に移すことに決まった。
家に着き、ストレッチャーが車から降ろされると、母はほほえみを浮かベ、何度も領くようにして、深緑の草木を見つめ、その上で木もれ陽が、うかれるように揺れていた。
畳の上に敷かれたふとんに体を横たえられると、母は「うれしい」と明るい笑顔を見せ、病室では、一人で体を動かすことも出来なかったのが、寝返りをうち、手や足を畳に触れて、懐かしそうに家の中の物音に耳を傾けていた。またいつもの生活が始まる様な錯覚の中にいた私に、「帰りたくないなあ(病院に)。このまま家で…」と言いかけて、母は口をつぐんだ。その声にならない言葉の意味に、私は母の手を握りしめ、無言で応えた。
もしもIVHをしていたら、命は何日延びたのか。そして、母の、あのほほえむ様な死顔を、同じように見れただろうか。−−−否。