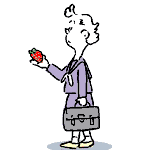 「明日、テストがあるから行けないわ」
「明日、テストがあるから行けないわ」 「何、言ってんだ!すぐ病院へ来い!」受話器から飛び出した伯父の怒鳴り声で、耳が破けそうだ。2週間前、緊急入院した母。「一体、何が起こったの?」病院までのタクシーの中、誰も喋べらない。伯母も。妹も。いとこも。窓から、春の黄昏が流れてゆく。3日前の父との会話が蘇った。「お母さん、いつ退院するの?」「秋ぐらいかなあ。お父さんだけじゃぁ嫌か?」聞き取れないほど、小さなつぶやきだっ た。
病院の廊下で待っていた父は、私と妹をかかえ込んだまま、ガクッと腰が崩れた。「ごめん。母さん、もう駄目なんだ」次の言葉はなかった。信じられない。夢だ。
しかし、病室に入った瞬間、それは現実となった。付添人の女性は、「これが、最後に口にした苺です。もう、喉を通りませんでしたが…」。暖かな部屋の中で、母は消え入りそうな息をしている。「お母さん!ひとみよ!目を開けて!」揺り動かすのを医師が制止した。「苦しかったでしょう。痛かったでしょう。どうか、神様、母を楽にしてやって下さい」。
夜が白む頃、母は一人旅立った。私が高校1年、妹が中学3年だった。カーテンを開けると街の信号は、まだ点減をしていた。春の嵐の日、挽歌が流れ、棺は進んだ。100メートル先の県道まで花環が立ち、両脇には妹の同級性150人の黒い制服が並んだ。傘も吹き飛ぶ強い風、わらじ 母の涙のように落ちて来る雨に向い、何度も心で叫んだ。「さようなら、お母さん。16年間、本当に有難うございました」。あれから11年。赤い苺を見るたびに、荒れ狂った空の下、私の青春と母の葬儀をなつかしく思い出している。